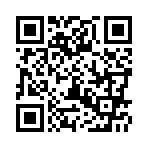2009年11月05日
M60リアルパーツ フィードトレイ
M60を分解整備中、ふとリアルパーツのフィードトレイをイノカツM60ボディに取り付けできるかな?と思い、試してみたところ給弾口のパーツを外すだけで簡単に取り付ける事が出来ました。給弾口のパーツを外しているのでマガジンは装着できませんが、ベルトリンクのダミーカートが自重で外れずしっかりと装着出来るので鑑賞用には最適です。
カートリッジが押し込まれる溝部分に給弾口が干渉するので取外しています。

ベルトリンクを装着、サイズもピッタリ。
(写真の図ではベルトリンクの向きが逆でした。)

フィードカバーを閉じた様子。ボックスマガジンを取り付けるとより雰囲気が出そうです。

純正パーツとの比べっこ。純正パーツは真ん中部分が長方形にくり抜かれています。

横からの図。両方後期型の形になっています。

裏側からリアルパーツを見てみたところ。少し出ているリム部分をボルトでチャンバーに押し出されていきます。

リンク排出部分上部にはアッセンブルナンバーの刻印。

じっくり見ていくと、各部分に補強や排出しやすいようにアール、テーパーを掛けていたりと様々な工夫が見られ興味深い一品でした。
おまけ・・・Mk43の傍らで感慨深く季節の移り変わりを感じる営業部長レオ君。

カートリッジが押し込まれる溝部分に給弾口が干渉するので取外しています。

ベルトリンクを装着、サイズもピッタリ。
(写真の図ではベルトリンクの向きが逆でした。)

フィードカバーを閉じた様子。ボックスマガジンを取り付けるとより雰囲気が出そうです。

純正パーツとの比べっこ。純正パーツは真ん中部分が長方形にくり抜かれています。

横からの図。両方後期型の形になっています。

裏側からリアルパーツを見てみたところ。少し出ているリム部分をボルトでチャンバーに押し出されていきます。

リンク排出部分上部にはアッセンブルナンバーの刻印。

じっくり見ていくと、各部分に補強や排出しやすいようにアール、テーパーを掛けていたりと様々な工夫が見られ興味深い一品でした。
おまけ・・・Mk43の傍らで感慨深く季節の移り変わりを感じる営業部長レオ君。

2009年08月25日
M60メンテナンス その3
バレル、ボルトアッセンブリー、エアスイッチやフレーム本体のクリーン&オイルメンテナンスや各部のネジが緩んでいないかチェックが終わりましたら、今度は取り外しの逆の手順で組み上げて行きます。
メンテナンスが終わった各部主要パーツと本体フレーム。

まずボルトアッセンブリーとリコイルスプリングをフレームに入れます。
フィードトレイを上に上げておき、出来るだけチャンバー側の前の方へと入れておきます。

エアスイッチの穴にドライバーを入れておき、本体フレームに入れていきます。

ボルトアッセンブリーが自重で下に落ちてエアスイッチを入れずらくなるので、持ち上げておきます。

ボルトを持ち上げつつ、取り外しの反対の手順で、エアスイッチに差し込んだドライバーでエアスイッチを組み込み、ロックを掛けます。

エアスイッチのロックが掛かる部分。
もしロックが掛かりづらい、入らないという場合はこの穴の外周にリューター等でバリやめくれ部分を整えておきます。
また、無理やり入れようとすると写真のようにエアスイッチと連結しているトリガーバーにダメージが出るので注意して下さい。

エアスイッチのロックがきちんと掛かったら、エアスイッチ部分にホースを接続しておきます。

次はバレルアッセンブリーを取り付けます。ゆっくり慎重に差し込みます。

センターが上手い具合に出て、ボルト部分と簡単に連結が出来ました。

エアシャフトに差し込んでるプラスドライバーの先端をエアシャフト後部の凹み部分に当てておきます。
こうするとエアシャフトのセンターが出ている状態になります。

ゆっくりとボルトを下げて行きます。
プラスドライバーとエアシャフトの具合をよく見ながら下げて行けばエアシャフトがエアスイッチに難なく入ります。

最後まで下げていくと、エアスイッチからエアシャフトがしっかり出てきます。

エアシャフトを通した後は、バレルアッセンブリーをしっかりと最後まで差し込みます。

パットプレートを取り付けて、フィードカバーを閉じてチャージングハンドルを引いて動きに問題は無いかチェックします。

ホースの先端、あるいはソケット部分にシリコンを一吹きしておくとエンジン全体にシリコンが浸透していきます。
最後にレギュレーターに取り付けて、作動チェックをして問題が無ければ完成です。
もし、問題点がある場合、エアスイッチの取付のロックがかかっていない、トリガーバーを押し付けている状態が多いので、その時はまた組み直しておきます。

最初はエアスイッチの取付、取り外しが難しいですが、馴れればものの数秒で出来てしまいます。何事も馴れと経験が大切となりますね。
メンテナンスが終わった各部主要パーツと本体フレーム。

まずボルトアッセンブリーとリコイルスプリングをフレームに入れます。
フィードトレイを上に上げておき、出来るだけチャンバー側の前の方へと入れておきます。

エアスイッチの穴にドライバーを入れておき、本体フレームに入れていきます。

ボルトアッセンブリーが自重で下に落ちてエアスイッチを入れずらくなるので、持ち上げておきます。

ボルトを持ち上げつつ、取り外しの反対の手順で、エアスイッチに差し込んだドライバーでエアスイッチを組み込み、ロックを掛けます。

エアスイッチのロックが掛かる部分。
もしロックが掛かりづらい、入らないという場合はこの穴の外周にリューター等でバリやめくれ部分を整えておきます。
また、無理やり入れようとすると写真のようにエアスイッチと連結しているトリガーバーにダメージが出るので注意して下さい。

エアスイッチのロックがきちんと掛かったら、エアスイッチ部分にホースを接続しておきます。

次はバレルアッセンブリーを取り付けます。ゆっくり慎重に差し込みます。

センターが上手い具合に出て、ボルト部分と簡単に連結が出来ました。

エアシャフトに差し込んでるプラスドライバーの先端をエアシャフト後部の凹み部分に当てておきます。
こうするとエアシャフトのセンターが出ている状態になります。

ゆっくりとボルトを下げて行きます。
プラスドライバーとエアシャフトの具合をよく見ながら下げて行けばエアシャフトがエアスイッチに難なく入ります。

最後まで下げていくと、エアスイッチからエアシャフトがしっかり出てきます。

エアシャフトを通した後は、バレルアッセンブリーをしっかりと最後まで差し込みます。

パットプレートを取り付けて、フィードカバーを閉じてチャージングハンドルを引いて動きに問題は無いかチェックします。

ホースの先端、あるいはソケット部分にシリコンを一吹きしておくとエンジン全体にシリコンが浸透していきます。
最後にレギュレーターに取り付けて、作動チェックをして問題が無ければ完成です。
もし、問題点がある場合、エアスイッチの取付のロックがかかっていない、トリガーバーを押し付けている状態が多いので、その時はまた組み直しておきます。

最初はエアスイッチの取付、取り外しが難しいですが、馴れればものの数秒で出来てしまいます。何事も馴れと経験が大切となりますね。
2009年08月21日
M60メンテナンス その2
前回のバレルアッセンブリーから、今回は本体側のメンテナンスに移って行きたいと思います。
エアスイッチやエンジン周りを取外すのに馴れない内は時間が掛かりますが、後述で紹介するコツをつかめば簡単に取外しが行えるようになります。
まずはバレルアッセンブリーを引き抜いた状態の本体。バレルが無いとランチャーにも見えなくも。

フィードカバーを開け、後部のストックを外して、エアスイッチに接続されているホースを抜きます。

フィードトレイ部分を持ち上げて、エンジン部分をチャンバー側に移動させてエアシャフトをエアスイッチの通る穴から外しておきます。

空いたエアスイッチの穴に、長めのプラスドライバーをエアスイッチ内部を傷つけないように差し込みます。

写真のような持ち方でプラスドライバーを起点にしてエアスイッチ部分を前に押し出し、内部のロックを解除させます。

ロックが外れたら、同じくプラスドライバーを起点にしながら上に持ち上げて引っ張るとエアスイッチ部分が引き出されます。
このプラスドライバーを用いた引き出し方法のコツを掴むと、すぐに取外し、取付が出来るようになり、またエアスイッチのロック部分もしっかり掛けれるようになります。

エアスイッチを取外し、スプリングやボルトアッセンブリーを取外して行きます。取り出したパーツはパーツクリーナーで汚れを落としておきましょう。
また、ボルトアッセンブリーのネジの増し締め、緩んでいたりしていないかのチェックもしておきます。

インパクトリングのネジもチェックしておきます。
ボルトアッセンブリーとなるエンジン各部のネジはM60のリコイルの反動、衝撃で緩んだりする場合があるので用途に合わせて、ロックタイトやネジゆるみ止め剤を塗布しておくのもよいでしょう。

エンジンのクリーン、オイルメンテナンスが終わったら、本体フレーム内部のチェックです。
真鍮の削り粉や細かいゴミが隙間から入りやすいので、パーツクリーナーや細かい筆やハケ等で掃除しておきましょう。
この際に、コッキングレバーを止めてあるネジも緩んでいないかチェックしておきます。

フィードカバー裏のピン部分のネジもチェックしておきます。フィードトレイ、マガジン給弾口を押さえる役目も持ち合わせているので、緩んでいるときちんと押さえ込みが出来ない場合があるので気をつけて下さい。

ハンドガード、ガスチューブ周り、グリップ周辺のネジの緩みが無いかチェックし、問題が無ければ本体フレームのメンテナンスは大丈夫です。ボルトアッセンブリーやエアスイッチ部分のパッキン類もしっかりオイルメンテナンスをしておきます。
次回は本体の組み付けに入ります。
エアスイッチやエンジン周りを取外すのに馴れない内は時間が掛かりますが、後述で紹介するコツをつかめば簡単に取外しが行えるようになります。
まずはバレルアッセンブリーを引き抜いた状態の本体。バレルが無いとランチャーにも見えなくも。

フィードカバーを開け、後部のストックを外して、エアスイッチに接続されているホースを抜きます。

フィードトレイ部分を持ち上げて、エンジン部分をチャンバー側に移動させてエアシャフトをエアスイッチの通る穴から外しておきます。

空いたエアスイッチの穴に、長めのプラスドライバーをエアスイッチ内部を傷つけないように差し込みます。

写真のような持ち方でプラスドライバーを起点にしてエアスイッチ部分を前に押し出し、内部のロックを解除させます。

ロックが外れたら、同じくプラスドライバーを起点にしながら上に持ち上げて引っ張るとエアスイッチ部分が引き出されます。
このプラスドライバーを用いた引き出し方法のコツを掴むと、すぐに取外し、取付が出来るようになり、またエアスイッチのロック部分もしっかり掛けれるようになります。

エアスイッチを取外し、スプリングやボルトアッセンブリーを取外して行きます。取り出したパーツはパーツクリーナーで汚れを落としておきましょう。
また、ボルトアッセンブリーのネジの増し締め、緩んでいたりしていないかのチェックもしておきます。

インパクトリングのネジもチェックしておきます。
ボルトアッセンブリーとなるエンジン各部のネジはM60のリコイルの反動、衝撃で緩んだりする場合があるので用途に合わせて、ロックタイトやネジゆるみ止め剤を塗布しておくのもよいでしょう。

エンジンのクリーン、オイルメンテナンスが終わったら、本体フレーム内部のチェックです。
真鍮の削り粉や細かいゴミが隙間から入りやすいので、パーツクリーナーや細かい筆やハケ等で掃除しておきましょう。
この際に、コッキングレバーを止めてあるネジも緩んでいないかチェックしておきます。

フィードカバー裏のピン部分のネジもチェックしておきます。フィードトレイ、マガジン給弾口を押さえる役目も持ち合わせているので、緩んでいるときちんと押さえ込みが出来ない場合があるので気をつけて下さい。

ハンドガード、ガスチューブ周り、グリップ周辺のネジの緩みが無いかチェックし、問題が無ければ本体フレームのメンテナンスは大丈夫です。ボルトアッセンブリーやエアスイッチ部分のパッキン類もしっかりオイルメンテナンスをしておきます。
次回は本体の組み付けに入ります。
2009年08月20日
M60シリーズメンテナンス その1
今回はM60シリーズの各部のメンテナンスやエアスイッチ、エンジンユニットの簡単な取付、取り外し方法を紹介して行きたいと思います。ブローバック系のガンは慣らし撃ちを終えた後やゲーム後のこまめなメンテナンスをして置くと、不意の動作不良やパッキン、チャンバーの汚れによる弾詰まり等のトラブル解消にも繋がります。
ボックスマガジンを取外した状態のM60E3。マガジンを予め外して置くとクリーニングがし易いです。

フィードカバーを開けて、バレルアッセンブリーを取外す準備をします。

通常の物では漏斗型の給弾ノズルを外してからバレルアッセンブリーを外します。
専用電動ガンユニットに戻したりする事が無い場合、エスコート社にて給弾ノズルを付けたままのバレルアッセンブリーの取り外し、取付が出来る加工を行っています。

取外したバレルアッセンブリー。

給弾ノズルをチャンバーから取り外し、ネジ山の部分をパーツクリーナーで汚れを落とします。

長く使っていると、ノズルのフチの部分が少しへこんだり、バリが出る場合があります。
このような場合はリューター等でフチ部分を削り過ぎないように慎重に形を整えて行きます。

チャンバーユニット側にも小さなバリや削れが出ている場合はノズル同様にリューターや丸ヤスリで形を整えます。
キレイに仕上がったらノズルを取り付けますが、ここでネジロック剤を使って完全固定してしまうと、リコイルの衝撃の逃げが無くなりノズルの根元が折れる場合があります。
この部分はボックスマガジンの給弾口とフィードカバーで上から押さえて固定する様になっているので、時々緩んできたら手で閉めなおすだけで大丈夫です。

ホップチャンバー部分も確認。MP5パッキン同様、慣らし撃ちをしていくとパッキンが程よく磨り減って2点支持のような形になります。どんどん使えば使うほどパッキンがBB弾の形状に馴染んだ最適な形になり弾道も比例して伸びが良くなります。

バレルアッセンブリーでは、給弾ノズル部分やホップパッキンやチャンバー部分のOリング、バレル内部のクリーニングが大事です。オイル汚れをパーツクリーナーで落として、シリコンオイルで再度オイルメンテンスをすればバレルアッセンブリー部分の通常メンテナンスは完了です。
次回はエンジンユニット、エアスイッチの取り外しに掛かります。
ボックスマガジンを取外した状態のM60E3。マガジンを予め外して置くとクリーニングがし易いです。

フィードカバーを開けて、バレルアッセンブリーを取外す準備をします。

通常の物では漏斗型の給弾ノズルを外してからバレルアッセンブリーを外します。
専用電動ガンユニットに戻したりする事が無い場合、エスコート社にて給弾ノズルを付けたままのバレルアッセンブリーの取り外し、取付が出来る加工を行っています。

取外したバレルアッセンブリー。

給弾ノズルをチャンバーから取り外し、ネジ山の部分をパーツクリーナーで汚れを落とします。

長く使っていると、ノズルのフチの部分が少しへこんだり、バリが出る場合があります。
このような場合はリューター等でフチ部分を削り過ぎないように慎重に形を整えて行きます。

チャンバーユニット側にも小さなバリや削れが出ている場合はノズル同様にリューターや丸ヤスリで形を整えます。
キレイに仕上がったらノズルを取り付けますが、ここでネジロック剤を使って完全固定してしまうと、リコイルの衝撃の逃げが無くなりノズルの根元が折れる場合があります。
この部分はボックスマガジンの給弾口とフィードカバーで上から押さえて固定する様になっているので、時々緩んできたら手で閉めなおすだけで大丈夫です。

ホップチャンバー部分も確認。MP5パッキン同様、慣らし撃ちをしていくとパッキンが程よく磨り減って2点支持のような形になります。どんどん使えば使うほどパッキンがBB弾の形状に馴染んだ最適な形になり弾道も比例して伸びが良くなります。

バレルアッセンブリーでは、給弾ノズル部分やホップパッキンやチャンバー部分のOリング、バレル内部のクリーニングが大事です。オイル汚れをパーツクリーナーで落として、シリコンオイルで再度オイルメンテンスをすればバレルアッセンブリー部分の通常メンテナンスは完了です。
次回はエンジンユニット、エアスイッチの取り外しに掛かります。
2009年07月11日
M60E3アウターバレル組替えモデル
M60E3アウターバレルをE4用アウターバレルに、ボックスマガジンもE4タイプに交換してみました。
バレル交換、各部位の交換が楽に出来るのもM60シリーズの利点です。
E4アウターバレル、マガジンを交換するとE3をスマートにしたような印象に。

アウターにはフルートがあり、キャリングハンドルも持ちやすい形になっています。

最大の利点、キャリングハンドルとリアサイトが干渉せずに済みます。

フロントサイトはとってもシンプル。細長いマンターゲットに見えるような、見えないような。

E3より装弾数が少ないですが横幅が無くなった分、ハンドガードとフォアグリップが楽に持てます。

マガジン裏側。給弾スイッチはゲーム時に使いやすい様に外側に配置換えしています。

パーツの互換性があるとあれこれ組替えてみたり、予備のスペアパーツとして使用したりできるのが嬉しい所です。
バレル交換、各部位の交換が楽に出来るのもM60シリーズの利点です。
E4アウターバレル、マガジンを交換するとE3をスマートにしたような印象に。

アウターにはフルートがあり、キャリングハンドルも持ちやすい形になっています。

最大の利点、キャリングハンドルとリアサイトが干渉せずに済みます。

フロントサイトはとってもシンプル。細長いマンターゲットに見えるような、見えないような。

E3より装弾数が少ないですが横幅が無くなった分、ハンドガードとフォアグリップが楽に持てます。

マガジン裏側。給弾スイッチはゲーム時に使いやすい様に外側に配置換えしています。

パーツの互換性があるとあれこれ組替えてみたり、予備のスペアパーツとして使用したりできるのが嬉しい所です。